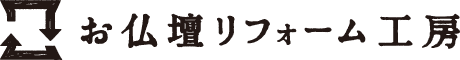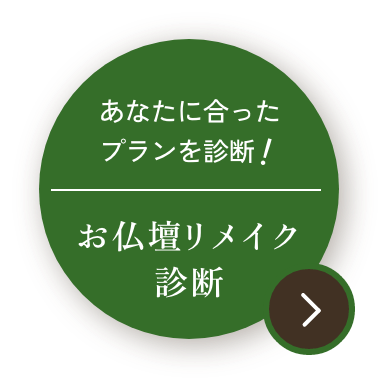お仏壇の歴史と現代の役割
お知らせ・情報
お知らせ・情報

そもそも「仏壇」って何?

実はお仏壇って何なのか、よくわからない方も多いのでは?
今回は2回にわたって、お仏壇についてご紹介します。
1回目は「お仏壇とは何か」と「お仏壇の歴史」についてです。
■お仏壇とは?何のためにあるの?
お仏壇は、仏さま/ご先祖さまを祀り安置/供養する、お家の中の小さな寺院のような存在。
私たちは、仏さまの/ご先祖さまの"お家"だと考えています。
お仏壇は、お盆や命日などの仏教行事・先祖供養の中心となってきましたが
みなさんは、お仏壇をどの様に使っていますか?
・お仏像や掛軸をお祀りする
・ご先祖様のお位牌・過去帳などを安置する
・ごはんや故人が好きだったものをお供えする
・いい香りのお線香を焚く
供養する方法は、宗派やご家庭によってさまざまです。
供養することでご先祖さまとのつながりを保ち、亡くなった方へ感謝や思いを伝えることができます。
こうして、多くの方々が手を合わせて、先祖代々 祈りをつないできたのではないでしょうか。
また、お線香を焚き、日常的に手を合わせるといった行為は、心の落ち着かせることができ精神的な安定にもつながります。
更に、伝統や文化を受け継ぐことで
仏壇を通じてお子さんやお孫さんが「命のつながり」や「感謝の心」を学ぶ場にもなっている様です。
■お仏壇のはじまりから、現代まで
・飛鳥時代
お仏壇の始まりは、7世紀の飛鳥時代までさかのぼります。
仏さまはお寺でお祀りするのが普通でしたが
貴族や武家のが自らの家に、仏教信仰の場として「持仏堂(じぶつどう)」と呼ばれる仏堂を作り、仏さまをお祀りしました。
それが"お仏壇"の源流ともいわれているそうです。
・江戸時代
この時代では、「寺請制度(てらうけせいど)」が導入され、すべての人がどこかのお寺の檀家なることになりました。
そのためお葬式など「信仰と先祖供養の拠点」が必要になり、持仏堂から発展して「お仏壇」(ご先祖さまを祀る場)という形に。
それに合わせてお仏壇は「ご本尊・お位牌・お仏具」を『まとめて安置する祭壇』として、寺院の祭壇を小型化したような存在に。
更に、細やかな彫刻や、漆や金箔を用いた装飾が施され、大きく荘厳な形になっていきました。
先祖供養を大切に思っているからこそ、立派なものにしたい。という想いがあったのかもしれません。
・明治/昭和時代
明治以降には、庶民の家にお仏壇が広く普及していき、昭和の頃までは「家に仏壇があるのが当たり前」になりました。
・現代
今は、伝統的な形のお仏壇だけではなく
家具調で洋室に合うモダンな仏壇や、省スペースで置けるコンパクトな仏壇なども多く販売されています。
お仏壇は“祈りや感謝の気持ちをカタチにする場”という役割は昔も今も変わらず、お仏壇は家族の思いをつなぐ大切な存在です。
忙しい日々で、毎日手を合わせる時間が無い方も、少しだけ手を合わせてみませんか?
髙橋
 一覧へ戻る
一覧へ戻る