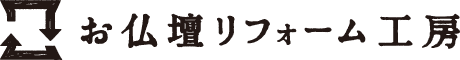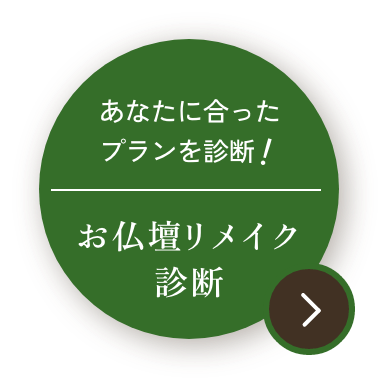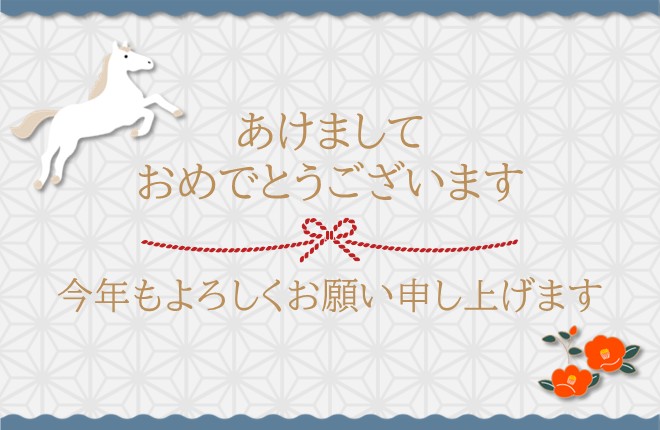【お盆前に知っておきたい③】「迎え火」とは?
お知らせ・情報
お知らせ・情報

意味ややり方、現代の工夫まで

お盆が近づくと、「迎え火(むかえび)」という言葉を耳にすることがあります。
「聞いたことはあるけれど、どんな意味があるの?」「どうやってやればいいの?」と、実際にはよくわからない…という方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、お盆の大切な習わしである「迎え火」について、意味ややり方、そして今の暮らしに合わせた工夫までわかりやすくご紹介します。
■ 迎え火とは?
迎え火とは、お盆の初日にあたる 8月13日(または7月13日) に、ご先祖さまの霊が迷わず我が家に帰ってこられるように、火を灯して道しるべとする伝統的な風習です。
門口や玄関先で焙烙(ほうろく)という素焼きの皿にオガラ(麻の茎)を置き、火をつけて煙を立てるのが古くからの一般的なやり方です。
火や煙は、ご先祖さまの霊がこの世へ戻ってくるための“目印”となり、「どうぞお戻りください」というご家族の想いが込められています。
■ 送り火とセットで行う供養
お盆が終わる 16日(または15日) には「送り火(おくりび)」を焚いて、ご先祖さまを再びあの世へとお見送りします。
迎え火と送り火は、お盆の始まりと終わりを示す大切な儀式であり、ご先祖さまを心から迎え、見送るという日本人の優しい供養のかたちです。
■ 現代の暮らしに合った迎え火の方法
マンションや住宅事情で実際に火を焚くのが難しいというご家庭も多いのではないでしょうか。
そんなときは、ろうそくの灯りや、LEDライトのお迎え火セットなどを使うのも現代ならではの方法です。
また、玄関に提灯を飾ることで「お迎え」の気持ちを表すご家庭も増えています。
大切なのは形よりも、ご先祖さまを想い迎える“こころ”。その気持ちを持って手を合わせることが何よりの供養になります。
■お盆を機に、お仏壇の佇まいを見直してみませんか?
お仏壇リフォーム工房では、お客様の想いに寄り添いながら、これからもご先祖さまとのつながりを大切にできるご提案をしております。どうぞお気軽にご相談ください。
 一覧へ戻る
一覧へ戻る