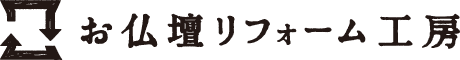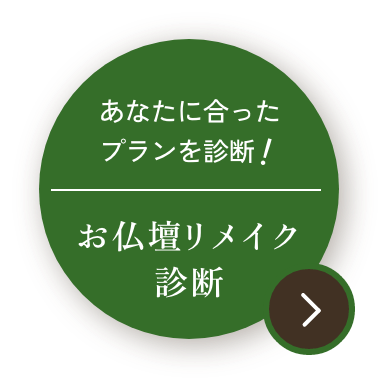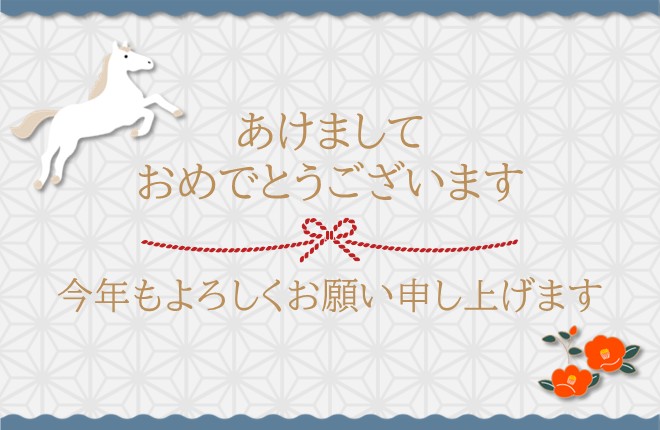「中秋の名月(十五夜)」とは?
お知らせ・情報
お知らせ・情報

「中秋の名月」について

■「中秋の名月」とは?
日本には、「十五夜」という伝統的な月見の行事あり、「十五夜」にはお月見をしてお団子を供え食べるという風習が根付いています。
しかし本来「十五夜」とは、月に関係なく旧暦での15日の夜のこと。
毎月満月に近い日ですが『月見をする日』ではありません。
十五夜の中でも、旧暦8月15日は「中秋の名月」と呼ばれ
“空が澄み渡り、月がクッキリと見える”
などの理由から、1年で最も美しい月を見ることができるとされています。
今年(2025年)は10月6日がその「中秋の名月」にあたります。
■中秋の名月にお月見をする理由
なぜ、中秋の名月にお月見をするか知っていますか?
まんまるに満ちた「満月」は『豊穣(ほうじょう)』や『幸せ』のシンボルとされています。
今も昔も「収穫」は命に係わる大事なことです。
昔の人は、作物が収穫できるということに対して、自然への感謝を込めて月にお供えをしていました。
そのため1年で最も美しい満月に、秋の収穫を感謝するという風習として始まったそうです。
美しい月を見ながら、自然と命に「ありがとう」を伝える、大事な行事なのですね。
■十五夜の風習
いつしか、旧暦8月の十五夜である中秋の名月に、お月見をする。ということ自体が「十五夜」と呼ばれるよことが多くなりましたが、みなさんは十五夜に何をしますか?
月見団子を15個お供えする?
ススキを飾る?
サトイモなどの秋の収穫物をお供えする?
私はおばあちゃんが作るお団子が大好きで、「お団子をお供えする日」ではなく「お団子を食べる日」だと思っていました。
いやはや、お恥ずかしい・・・。
そう思っていましたが、調べてみるとあながち間違いではないようです!
お団子を供えるということには「悪いことを避け、健康を願う」という意味がありました。
一通り月を眺めてお祈りしたあと、お供えしたお団子を家族で食べることで“福を分け合う”ことができるとされています。
おばあちゃんのお団子がおいしかったのは、お月さまパワーが宿ったお団子だったからかもしれませんね。
■「十三夜」とは?
そして、忘れてはいけない「十三夜」。
「中秋の名月」に次いで美しいとされているのが「後の月」と呼ばれる「十三夜」です。
「後の月」は旧暦9月13日の月のことで、今年(2025年)は11月2日にあたります。
十五夜だけ、あるいは十三夜だけ見ると「片見月(かたみづき)」といって縁起が悪いとされることもあります。
なぜかというと、十五夜と十三夜はセットで『二夜の月』といい、両方見ることで月見が完了するそうです。
そこから、片方のみお月見をすると途中でやめたことになり【不完全=不吉】というとらえ方につながったとされています。
しかし現代では、「十三夜」の知名度は低く忘れられがちです。
秋は、運動会・文化祭・ハロウィンなどの行事が目白押し。
さらに十五夜に対し、十三夜のイベントは少なく、メディアでも大きくは取り上げられません。
十五夜は中国伝来の行事ですが、十三夜は日本独自の風習です。ずっと守っていきたいですね。
■祈り心が込められた特別な夜
十五夜/十三夜は、自然への感謝と家族の健康や幸せを願う、静かな祈りの夜です。
忙しい日々を送っているみなさまも、是非この夜だけは一緒に空を見上げてみませんか?
-

十日夜の月
因みに、旧暦10月10日は「十日夜」。 今年(2025年)は11月29日にあたります。 「十五夜」「十三夜」は2つセットで行うことで縁起がいいとされていますが、「十日夜」も含めると『三夜の月』といい、更に完全・円満・豊作祈願の意味が強まり、縁起がいいとされています。 10月は「神無月」と呼ばれ、神々が出雲大社へ集まる月です。そのため「田の神様が山へ帰る」と考えられ、旧暦10月10日が収穫への感謝する日になったそうです。
 一覧へ戻る
一覧へ戻る