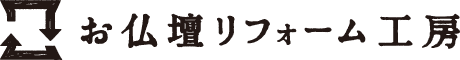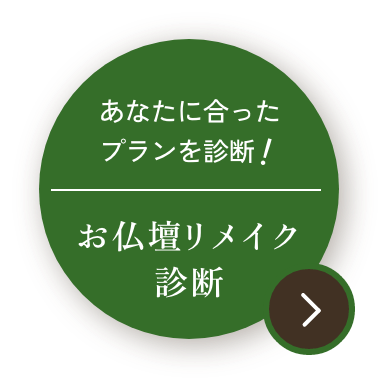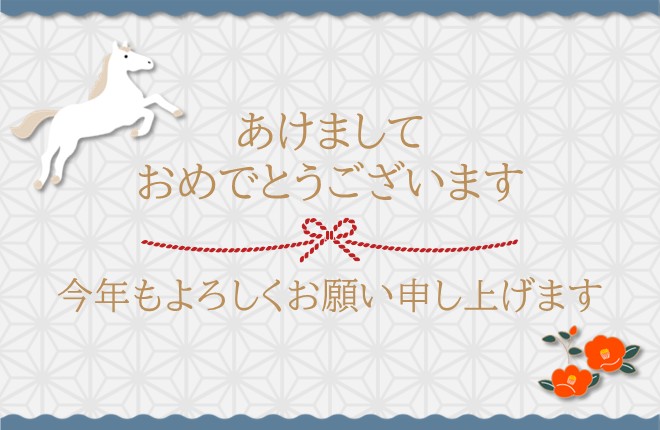牡丹餅とおはぎの話
お知らせ・情報
お知らせ・情報

お彼岸に欠かせない“あの味”

秋のお彼岸には、仏壇に果物やお花とともに、ある和菓子をお供えする風習があります。それが、「おはぎ」です。
もち米を炊いてつぶし、あんこで包んだ素朴な和菓子は、今も多くのご家庭で親しまれています。
ところで、「おはぎ」と「ぼたもち」は、何が違うのでしょうか?
実は材料や作り方はほとんど同じで、呼び名が季節によって変わるのが大きな特徴です。春のお彼岸には「ぼたもち(牡丹餅)」、秋には「おはぎ(お萩)」と呼ばれ、それぞれ春の花「牡丹」と秋の草花「萩」にちなんで名づけられました。どちらも自然や季節を感じる、美しい日本語の表現です。
また、あんこに使われる小豆の赤色は、古くから「魔除け」「厄除け」の力があると信じられてきました。お彼岸にあんこのお菓子をお供えするのは、ご先祖様への感謝とともに、家族の健康や無事を願う気持ちが込められているのです。
おはぎは、私たちの記憶の中にあるやさしい味。
お仏壇に供える際も、手作りや市販品にかかわらず、「想う心」がなによりの供養となります。
この秋のお彼岸、ご先祖様に感謝を伝えるひとときとして、おはぎをお供えしてみてはいかがでしょうか。
心を込めて手を合わせる――その行いが、今を生きる私たちの心もそっと整えてくれるはずです。
岩澤
 一覧へ戻る
一覧へ戻る